
Q1. 御社の投資哲学と追求されている収益源泉について、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
弊社は、日本で主たる事業を行う企業に対してメザニンファイナンスを行うPD(プライベートデット)ファンドであり、主な投資対象は、PEファンドや経営陣がLBOやMBOを行う際に買収資金を提供する「バイアウトメザニン」と、企業の債務再編の際や成長資金としてニューマネーを提供する「コーポレートメザニン」です。メザニンファイナンスは「シニアファイナンスより高く、エクイティよりも低いミドルリスク」を取る金融であり、利回りも「エクイティ利回り(凡そ20%)より低く、シニア利回(凡そ3%)の間」で、通常10%前後です。メザニンファイナンスの収益源泉は、シニアファイナンスが正常債権である場合に(即ち正常な運転資金や設備資金の貸出である)、それを超過する金額で、且つ「企業価値」の範囲内にあると考えます。「企業価値」は企業の将来収益の現在価値で見ますが、エクイティ投資家は株式売却により価値を実現しますので、市場価格や売却候補先の影響を大きく受けますが、メザニンファイナンスの場合は基本的に投資期間中に企業が稼ぐ超過収益だけで回収源泉を考えます。
従って、「業績が大きく悪化しない限りは投資回収の蓋然性を確保できる事業体」がメザニンファイナンスの投資対象として選定されます。尚、実際に回収するためには、「収益源泉を金銭化するためのストラクチャー」が必要となり、メザニンプレイヤーはこのファイナンスストラクチャーを吟味・構築できる能力を問われます。
Q2. その収益源泉を実現するために、どのような投資プロセスを採用されているのか、ご教示いただけますでしょうか。
メザニンファイナンスの収益源泉を決める要素は3つあり、一つ目はシニアファイナンスの金額、二つ目は企業価値、三つ目はファイナンスストラクチャーと考えます。一つ目のシニアファイナンスの金額は銀行が対象企業に対して取り得るリスクの範囲内であり、本来は市場の影響を受けない筈ですが、銀行間の競争環境が許容リスクに歪みを生じさせることもあるため、メイン行の動きを含めてシニアレンダーの動向に注意をして検討します。
二つ目の企業価値は対象企業の事業性によりますが、特に買収ファイナンスの場合はスポンサーの企業価値創出能力により対象企業の収益性が大きく変わりますので、スポンサー施策の蓋然性に最も注視する必要があります。結果的に過去の投資案件を通じて、ファイナンス条件やハンズオン内容、各局面での考え方を理解できているスポンサーと組むことが多くなります。
最後のファイナンスストラクチャーは「できるだけリスクが極小化される投資形態」の考察と「税制等の活用による手元流動性やFCF創出の可能性」を検討します。昨今は「劣後ローンや優先株式」に加えて「HoldCoローン」の投資形態が増えてきており、持ち株会社も国内のみならず海外を含めて複層化してきており、スキームリスクも収益源泉の回収方法も複雑化してきてます。一方、案件組成に関わるプロフェッショナルファームの知見も案件増加と共に洗練されてきていますので、検討体制は整っていると考えます。
Q3. ポートフォリオ・マネジャーとして最も重視されていることは何でしょうか。また、常に心がけていることや、逆にしないと決めていらっしゃることがあれば、ぜひお聞かせください。
ファンド創業以来一貫して「ポートフォリオ分散」を最も重視しております。各ファンドとも10件から15件の投資を行い、今日までに累積70件弱の案件に投資をしております。メザニンファンドは投資対象企業の経営権を握らずにリスクマネーを出しますので、万が一に投資回収リスクが顕在化した際でも能動的対応が限られるため、「リスク分散」を行うことが必須と考えます。投資判断の際に常に心掛けていることは、「定量的分析に偏り過ぎずに数字に出ない本質的リスクを見極めること」です。日本を代表する一流企業でもガバナンス問題が出ている中で、特に第三者が投資対象企業のガバナンス状況を全て的確に掴むことは容易ではなく、時間とコストを惜しまずに事前調査を行うことが肝要と考えます。弊社が取り組むノンスポンサー(PEがスポンサーとして入らない)案件は、大体1年から2年間の検討時間をかけております。
尚、「市場価格の変動リスクはメザニンが取れるリスクの範疇ではない」と整理しており、不動産売買業等の「市場価格変動と収益がリンクする事業」には投資をしないことにしております。
Q4. 日本市場にはどのような投資機会があるとお考えでしょうか。
日本のメザニンファイナンス市場は企業のM&Aが増えたことでこの数年間で急激に大きくなったために投資機会も増えております。今まではメインバンク制の名残で「シニアファイナンスが席巻」していたものが、徐々にその構造も変わりつつあり、欧米市場並みの「適正なリスクプロフィットのファイナンスの階層化」が進む可能性はあり、これからはメザニンファイナンスの対象も多様化すると思われます。直近の検討案件ベースでは年間5千億円の規模になり、ファンド創業時と比較すると隔世の感があります。但し、残念ながらメザニンファンドへの資金供給者はまだ十分いないと思います。現在投資期間中の日本の主要メザニンファンドのファンド総額は合計でも2千億円くらいですので、メザニンファイナンスの年間需要金額にも満たず、圧倒的な供給不足と考えられます。
一方で、供給不足であるが故にメザニンファイナンスには過当競争が起きていなく、投資家にとり魅力がある内容をつくることができる状況です。弊社のファンドは募集期間中の初期から新規投資を積み上げることで、決算初年度より黒字化を実現するように運営をしており、国内の機関投資家、特に年金基金には日本のメザニンファンドへのLP出資を切望致しております。
Q5. お客様の資産保全のためにどのような点に留意されているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
メザニンファイナンスですので、資産保全の基本は「担保取得と適時回収」となり、劣後ローンの場合はシニアファイナンスの担保の後順位設定を行いますが、優先株式の場合は担保取得ができませんので、「取得請求権や普通株式転換権」の設定により「適時回収」をできる設計をつくることが基本になります。尚、早期回収を行うと「投資回収倍率」が低くなりますので、投資後2年以内の回収についてはリサイクル投資を行うことで、資産保全と投資効率の両方を向上させております。当初のファンドでは「リサイクル投資」に重きを置いていなかったためにグロスIRRが10%以上でも、投資倍率が1.2倍を切る成績でしたが、直近ファンドでは既に投資倍率を1.3倍以上に引き上げることができております。又、前述の通り「ポートフォリオ分散」も、リスク分散による投資家の資産保全と考えており、LPとの協働投資、引き受け後のメザニンシンジケーションを行っています。
Q6. 現在と10年前とでは、経営者の考え方や投資環境にどのような変化があったとお考えでしょうか。
この10年間でメザニンファイナンスの認知度が格段に飛躍したと考えます。認知されるようになった一番の背景は「エクイティコストに対する理解」がステークホルダーの間で進んだことによると考えます。メザニンファイナンスの黎明期では「シニアを代替する高利ファイナンス」と見られネガティブなイメージが先行しておりましたが、最近ではそのような見方が徐々に少なくなり、代わって「メザニンファイナンスはエクイティを中期的(2~3年)代替するファイナンス」として、エクイティコストとの比較で見られるようになってきていると思われます。従って、オーナーによる事業承継でもメザニンファイナンス利用は増えてきており、メザニンファンドの投資機会が中堅中小企業においても拡大してきております。メザニンファイナンスの利用が中堅中小企業まで広がると、全国の地方銀行や信用金庫にまで認知されるようになりますので、次の10年間では、日本の機関投資家が日本のメザニンファンドにお金を振り向けるようになることを期待しております。
Q7. 日本企業の事業価値向上のために、企業が取り組むべきことや、金融業界としてどのような支援ができるとお考えでしょうか。
金融業界の一員としては、過去に発生した金融バブルを繰り返さないように「適正なリスク判断と適正なファイナンスを行う市場慣行」を作り上げることに尽きると考えます。海外プレイヤーが日本のメザニンマーケットに入ってくる際に為替メリットを生かして経済条件がダンピングされることがありますが、国内プレイヤーが対抗すると健全なファイナンス環境が崩れますので、プレイヤーの自律性に拠るところは大きいと考えます。メザニンファイナンスは、「リスクはあるが、顕在化する可能性は低い=メザニンとして取ることができるミドルリスク」の投資案件を選別するファイナンスです。メザニン業界の拡大のためには日本のメザニンプレイヤーが投資実績を積み上げて、日本の機関投資家の資金を呼び込むことで専門プレイヤーが増えることが必要ですが、同時にシニアレンダーもシニアファイナンスとリスクファイナンスを種別することで、金融界全体で「ファイナンスの階層化」を進めることが必要と考えます。これにより、機関投資家にとっても「取ることができるリスクファイナンス」の品揃えが増えることになり、最終的にリスクファイナンスが日本の企業に流れることでその事業価値の向上が実現されると考えます。
Q8. 投資に関するおすすめの書籍を1冊ご紹介いただけますでしょうか。書籍の概要・感想・評価についてもご教示いただけますと幸いです。
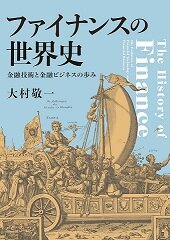
本書は十字軍や大航海時代の遠征資金の調達、ロンドンの金匠銀行に拠る信用創造(レバレッジ)の始まり、産業革命を通じて公共から民間への証券ファイナンスの拡大、民間エクイティファイナンスの勃興、19世紀初めの資本構造階層化からのメザニンファイナンスの登場、中流層への運用ニーズの拡大、南北戦争後のインベストメントバンクの登場、20世紀初頭のPE登場、サブプライムを含む今日の金融まで欧米のファイナンス市場の歴史書ですが、日本の金融との比較や、マイケル・ミケルソンの栄光と挫折等の有名人のコラムも随所に書かれており、大変読みやすい「投資の歴史書」です。
40年前の入社試験の際に銀行に入りたい事由として「銀行は信用創造ができる」と言っていたことを思い出しますが、この本を読むとファイナンスの長い歴史の中でも常に「レバレッジ」が「信用創造」の核であり、同時に具現化された「レバレッジファイナンス」の歴史はまだ短く、これからも色々な変化が予見されることを学ぶと思います。
インタビューは以上になります。
リスク・手数料などの重要事項に関するご説明
